【保存版】SNS×案件獲得の完全マニュアル:媒体別戦略まとめ
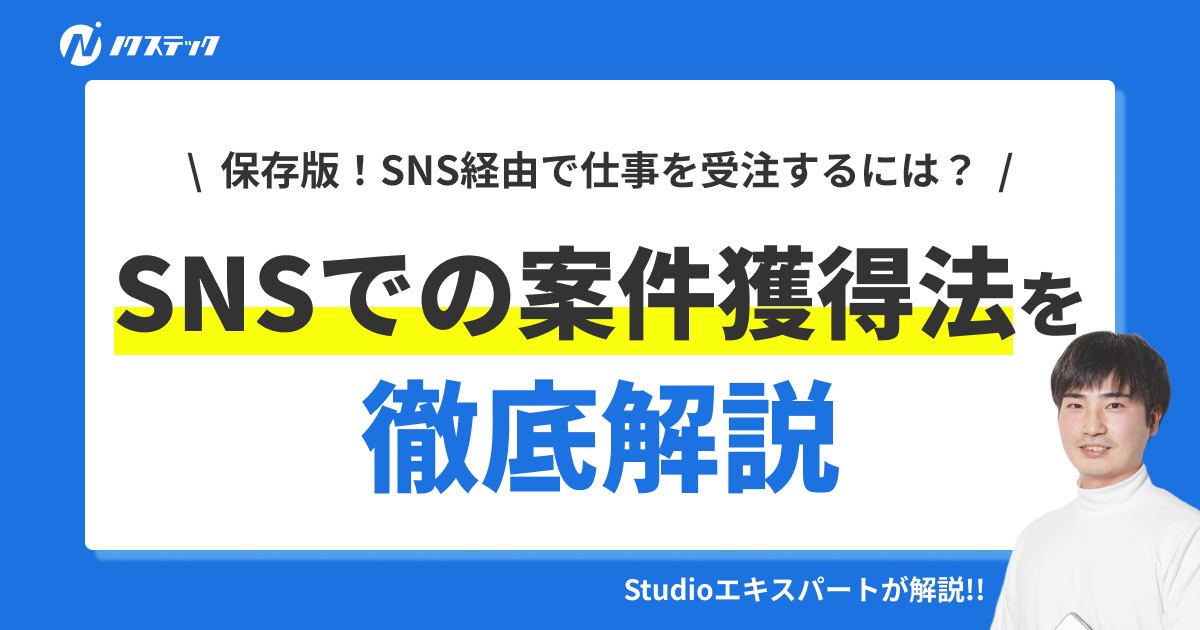
「SNSをもっと活用して、安定的に案件を獲得したい」
そう考えているWebデザイナーの方は多いのではないでしょうか。
実績が増えてきた今こそ、SNSでの発信を通じて“選ばれる存在”になることが、継続案件や高単価化につながります。
本記事では「案件獲得 SNS」というキーワードを軸に、SNS運用の考え方や各プラットフォームでの発信ポイントを丁寧に解説します。
この記事はStudio相談実績200件超の実績があるStudioエキスパートが経験を元に執筆しておりますので、ぜひ最後までお読みください。
本記事では「案件獲得 SNS」をテーマに、中級者WebデザイナーがSNSを活用して仕事を獲得するための戦略を解説しています。
各SNSの特性を理解し、媒体ごとに発信方法を最適化することで、信頼構築と集客効率を高めることが可能です。SNSごとの発信ポイントや導線設計、フォロワーとの関係構築など、すぐに実践できる具体策を紹介しています。
これからSNS集客を本格化させたい方は、まず本記事からスタートしてみてください。
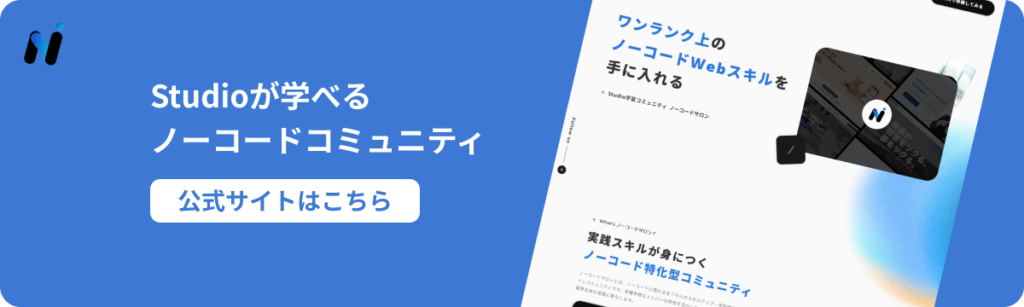
SNSで案件獲得するための考え方3選
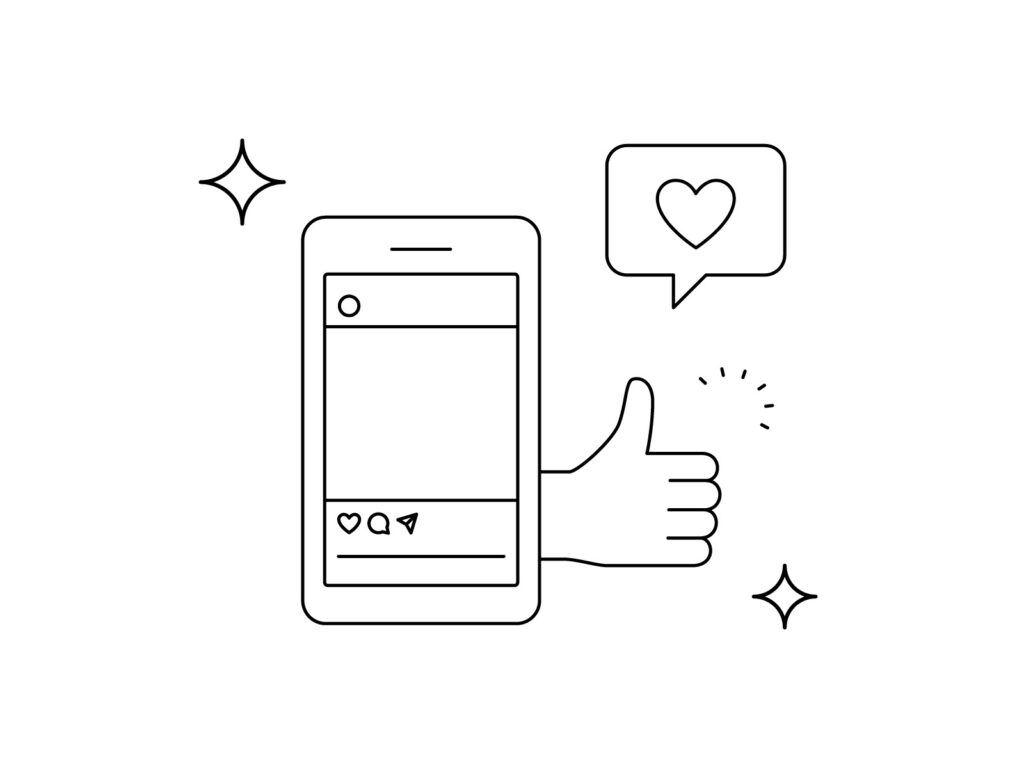
SNSで案件獲得するための考え方は以下となります。
順番に説明していきます。
参考:【初心者必見】Webデザイナーが案件獲得につなげる差別化方法5選
考え方1. フォロワーではなく「見込み顧客」を集める
案件獲得を目的としたSNS運用では、フォロワーの数よりも「誰に見られているか」が重要です。
単に数字を追うのではなく、自分が受けたい仕事・関わりたい業界の人に届く発信を意識しましょう。
ターゲット層に響く内容に絞ることで、案件に直結する反応が得られやすくなります。
「この人に頼みたい」と思わせる情報を届けることが最優先です。
考え方2. SNSは「資産型ポートフォリオ」になる
SNSに投稿した内容は、蓄積されることでポートフォリオのような役割を果たします。
「こんな制作ができます」「このように考えて提案しています」といった発信を重ねれば、信頼の土台になります。
投稿を見たクライアントが、「この人の実績や考え方は信用できそう」と感じる流れを作ることが可能です。
自分の専門性を定期的に発信することで、“発信=営業ツール”になります。
考え方3. 発信は“誰のためか”を明確にする
日々の投稿を「誰のために発信しているのか」が曖昧だと、ターゲットの心に響きません。
「個人事業主向けにWebサイト制作を提案したい」「美容業界に特化したLPを作っている」など、具体的に想定することで発信が洗練されます。
狙う市場や届けたい人が明確になれば、自然と投稿内容・トーン・デザインも整っていきます。
SNSは“見つけてもらう”場なので、まずは「誰に見つかりたいか」を決めることが出発点です。
各SNSの特徴と使い分け方法5選
各SNSの特徴と使い分けは以下となります。
- X(旧Twitter):即時性と拡散力に優れる
- Instagram:ビジュアル訴求で世界観を伝える
- Threads:関係構築重視のつながりが生まれやすい
- YouTube:制作過程やノウハウを伝える資産型媒体
- note:文章で信頼構築できるブログ的媒体
順番に説明していきます。
参考:【最新】X経由で案件獲得する方法とは?モニター募集で業務委託のクライアントを獲得する方法も解説!
方法1. X(旧Twitter):即時性と拡散力に優れる
Xは140文字という短文の投稿で、リアルタイム性や拡散力を活かした発信が得意な媒体です。
トレンドを取り入れたり、実績報告や気づきを素早く共有したりすることで注目を集められます。
また、リプライや引用リポストによってフォロワーとの距離を縮めることも可能です。
ポートフォリオへの導線をしっかり設けておけば、案件獲得にもつながりやすくなります。
方法2. Instagram:ビジュアル訴求で世界観を伝える
Instagramは、画像やリール動画を使って“世界観を視覚で伝える”のに優れたSNSです。
デザインの雰囲気やブランド感、UIの一貫性など、視覚情報を活かした訴求に強みがあります。
ストーリーズやハイライトを活用することで、実績紹介やQ&A、依頼の流れなども常設可能です。
中級者Webデザイナーとしての「見せ方」を洗練させたいなら必須のSNSです。
方法3. Threads:関係構築重視のつながりが生まれやすい
Threadsは、まだ競合が少ない分、関係性の濃いフォロワーが集まりやすい特徴があります。
カジュアルかつ真摯な投稿が歓迎されやすく、会話ベースで信頼関係を築きやすいのが魅力です。
投稿の拡散よりも「共感」と「交流」が重視される文化のため、固定ファンを作るには向いています。
他SNSと併用しながら、関係構築用の窓口として活用すると効果的です。
方法4. YouTube:制作過程やノウハウを伝える資産型媒体
YouTubeは動画という媒体の特性上、深い情報を届けやすく、視聴者との信頼を長期的に築けます。
「制作の裏側」「ビフォーアフター解説」「ノーコードツール”Studio”での実装例」などが人気のテーマです。
動画の内容がSEOにも寄与するため、検索からの流入を狙える点も大きな強みです。
工数はかかりますが、積み上げれば案件獲得への強力な資産となります。
方法5. note:文章で信頼構築できるブログ的媒体
noteはブログ感覚で使えるSNSであり、文章によって思想や過去の経験を丁寧に伝えたい方に向いています。
ポートフォリオだけでは伝えきれない「なぜそのデザインにしたか」「どんな想いで仕事に向き合っているか」を記録できます。
実績の深掘りやノウハウ共有の場として継続していけば、指名相談につながることもあります。
特に中級者以降は、自分の言語化力も差別化ポイントになるため活用価値は大きいです。
また、案件獲得コンサルでは、SNSでの案件獲得方法もレクチャーしています。
>案件獲得コンサルで低単価から抜け出す方法を身につけるためにLINE登録する
SNSから案件につなげる導線設計4選
SNSから案件につなげる導線設計は以下となります。
順番に説明していきます。
参考:【2025年最新】フリーランスデザイナーの案件獲得方法10選〜未経験からでも月収50万円を目指せる方法
導線設計1. プロフィール設計で信頼を獲得する
SNSプロフィールは、見込み顧客があなたを判断する最初の接点です。
「何をしている人なのか」「誰に何が提供できるのか」を簡潔に書き、信頼感のある肩書きにしましょう。
アイコン・ヘッダー・自己紹介文の3点を整えるだけでも、印象は格段に変わります。
さらに、実績や対応領域なども明記することで「この人に頼みたい」と思ってもらえる確率が高まります。
導線設計2. CTAを明確に設置する
「無料相談はこちら」「制作のご依頼はDMへ」など、行動を促す文言をプロフィールや投稿に必ず入れましょう。
CTA(Call to Action)がないと、フォロワーは次に何をしていいのか分からず離脱してしまいます。
リンクツリーや個人サイトへのリンク設置も有効で、選択肢を明確に示すことが重要です。
意外と多い“CTAなしアカウント”を脱して、仕事に直結する動線を設計しましょう。
導線設計3. ポートフォリオへの導線を整備する
どんなに良い発信をしていても、制作実績にすぐアクセスできないと機会損失になります。
ポートフォリオサイトやNotion・STUDIOなどで作成したページを、固定投稿やリンク欄に明記しておきましょう。
「プロフィール→ポートフォリオ→相談」の流れが自然につながるように設計することが大切です。
また、ポートフォリオの構成も「お客様の声」「ビフォーアフター」「目的別」で整理すると効果的です。
導線設計4. リプ・DM対応の導線を可視化する
SNSでは「相談はDMで受け付けています」と書いていても、DMを送るハードルが高い人も多いです。
そこで「〇〇の件、気軽にリプください」「〇〇の感想があればDMで聞かせてください」など、具体的な導線を提示しましょう。
投稿本文に“声をかけていい”空気を作るだけで、反応率が上がります。
また、自動返信ツールなどを使えば、対応の効率化も可能です。
案件獲得に効くSNSコンテンツの型4選
案件獲得に効くSNSコンテンツの型は以下となります。
順番に説明していきます。
参考:【最新】Webデザイナー必見の継続案件獲得方法を徹底解説!
型1. ビフォーアフター投稿
案件獲得につながりやすい代表的なコンテンツが「ビフォーアフター投稿」です。
「改善前→改善後」の流れを画像やテキストで見せることで、成果を直感的に伝えることができます。
クライアントにとって“何がどう良くなったか”が明確に伝わるため、信頼を得やすくなります。
自作課題でも構わないので、意識的にこの形式の投稿を増やすと効果的です。
型2. 制作過程の共有
完成品だけでなく、制作途中の設計意図や工夫を発信することで「この人は考えてデザインしている」と伝わります。
たとえば「なぜこの余白を取ったのか」「この構成にした理由」などを説明すると、思考力のアピールにもなります。
“過程”にこそその人の強みが表れるため、実績が少ない方でも取り組みやすい手法です。
継続的に投稿すれば、ストーリー性も出てきてファンも生まれやすくなります。
型3. 実績+お客様の声紹介
納品後にクライアントから感謝の言葉をもらった場合、それをセットで投稿することで強い信頼コンテンツになります。
「成果を出した×お客様の声」という組み合わせは、第三者からの推薦に等しい効果があります。
もし実案件がない場合でも、モニターや知人に協力してもらい“声”を集めることで信頼を高めることができます。
文章+スクショの組み合わせ投稿もおすすめです。
型4. 課題提起とミニアドバイス投稿
「◯◯でお困りではありませんか?」という課題提起から始めて、その簡単な改善策を発信する形式は、専門性の高さと親切さを両立できます。
ミニコンサルのような投稿は、フォロワーの信頼を得やすく、保存・シェアもされやすい傾向があります。
さらに「詳しくはDMでアドバイスします」と繋げることで、直接のやり取りにもつなげられます。
価値提供型の発信を意識して投稿の質を高めましょう。
案件獲得コンサルでは、SNSの投稿内容も実績あるコンサルタントがレクチャーします。
>案件獲得コンサルで低単価から抜け出す方法を身につけるためにLINE登録する
SNSごとの案件獲得のポイント5選

SNSごとの案件獲得のポイントは以下となります。
- X(旧Twitter):共感+拡散型で信頼を得る
- Instagram:世界観とビジュアルで魅せる
- Threads:親密感を活かして交流を深める
- Facebook:コミュニティを活かして提案する
- YouTube:ノウハウ動画で専門性を伝える
順番に説明していきます。
参考:【初心者必見】Webデザイナーが案件獲得につなげる差別化方法5選
ポイント1. X(旧Twitter):共感+拡散型で信頼を得る
Xは「拡散力」が最大の特徴です。
感情に寄り添う投稿や、制作の裏側など共感性の高い内容がリツイートされやすく、短期間で認知を広げることができます。
信頼を得るためには、日々の発信に「実績」「思考」「人柄」をバランスよく混ぜるのがポイントです。
プロフィールと固定ポストを整えて、案件相談の導線をしっかり設計しておきましょう。
ポイント2. Instagram:世界観とビジュアルで魅せる
Instagramでは、視覚で“魅せる力”が求められます。
ビジュアルの一貫性や色使い、デザインの洗練度が重要で、作品の世界観が整っているほど信頼されやすくなります。
投稿のキャプションには、「誰に向けて・何を意識したデザインか」を簡潔に添えると、価値が伝わりやすくなります。
ストーリーズやハイライトで、DM相談への導線を設けるのも忘れずに。
ポイント3. Threads:親密感を活かして交流を深める
ThreadsはXよりも少人数・深めのつながりを築きやすいSNSです。
フォロワーとの対話や雑談の延長線上で仕事の話が生まれるケースも多く、フランクさと誠実さのバランスが重要になります。
作品紹介というよりは「想い」「工夫」「課題意識」を語る場所として活用すると効果的です。
リアルタイムな交流がしやすいため、フォロワーとの信頼関係構築に向いています。
ポイント4. Facebook:コミュニティを活かして提案する
Facebookでは、グループ・イベント・知人経由のつながりが仕事に直結しやすい特徴があります。
プロフィールにポートフォリオや活動内容を掲載し、仕事につながりやすい人脈にリーチするのがポイントです。
グループ投稿やコメント欄での丁寧なやり取りが、「この人にお願いしたい」という印象につながります。
自己紹介+実績紹介の投稿を定期的に更新すると、効果的な露出が得られます。
ポイント5. YouTube:ノウハウ動画で専門性を伝える
YouTubeは長期的に信頼を育てられる媒体です。
「◯◯のデザインを改善してみた」「初心者向けWeb制作講座」などのノウハウ動画は、あなたのスキルを証明する強力なコンテンツになります。
動画の冒頭に実績紹介やLINEへの導線を加えると、視聴者が行動を起こしやすくなります。
SEOとも相性が良いため、「SNS 案件獲得」などのキーワードをタイトルに含めて投稿しましょう。
まとめ|SNS活用で案件獲得の幅を広げよう
本記事では「案件獲得 SNS」というテーマで、中級者Webデザイナーが実践すべきSNS戦略を5つの視点から解説しました。
- 案件につながるSNS発信の基本設計
- 各SNSの特性を活かした発信のポイント
- プロフィールやCTAの整え方
- フォロワーとの信頼関係の築き方
- X・Instagram・Threadsなど各媒体での具体策
SNSは、ただ情報を発信するだけの場所ではなく、「信頼を積み重ね、仕事につなげる営業チャネル」です。
発信に自信がない場合でも、ターゲット設定や発信設計を見直すことで、着実に反応を得ることが可能です。
あなたの強みを正しく伝え、見込み顧客に届くよう、戦略的にSNSを活用していきましょう。
また、案件獲得コンサルでは各種SNSでの案件獲得方法をサポートします。
駆け出しから抜け出したい方も、これからにもっと弾みをつけたい方も、登録無料のLINEに参加してみませんか?
